カンファレンスの開催は、多くの企業や組織にとって重要な戦略の一つです。特に、グローバルな市場への進出を目指す場合、イベントは国際的な知見の共有、ブランド認知度の向上、そしてグローバルなネットワークの構築に不可欠です。この記事では、海外進出を目指すイベントの開催方法について、準備から実施、フォローアップまでの全過程を詳しく解説します。
カンファレンスとは
カンファレンスとは、特定の分野や関心事項に関する知識や情報を共有し、議論や交流を行うためのイベントのことです。
カンファレンスの目的は、知識や経験の共有、ネットワーキング、情報収集などにあります。参加者は最新情報を入手でき、発表者は研究の評価を受けられ、企業は新製品のPRやマーケティングができるなどのメリットがあります。
カンファレンス海外開催のメリット
カンファレンスを海外で開催するメリットは以下の3つです。詳しく解説します。
- グローバルなネットワークの構築
- 国際的な知見の共有
- ブランドの国際的な認知度向上
グローバルなネットワークの構築
海外でのカンファレンス開催は、世界各地からの参加者との接点を生み出し、グローバルなネットワークを構築する絶好の機会です。構築したネットワークは、新しいビジネスチャンスの創出、異文化間の理解促進、さらには将来的なパートナーシップの基盤となり得ます。特に、異業種間のコラボが求められる現代において、多様なバックグラウンドを持つ人々との交流は、革新的なアイデアやソリューションの創出につながります。そのため、ネットワークを構築するためにカンファレンスを構築することは効果的です。
国際的な知見の共有
カンファレンスは、最新の研究成果や業界のトレンドを共有する場でもあります。海外での開催により、異なる国や地域での成功事例、挑戦、解決策などを学ぶことができ、これらの知見は参加者自身の業務やプロジェクトに活かすことが可能です。また、国際的な視点を持つことで、自社の事業や製品をグローバル市場に適応させるための戦略を練る上での重要な洞察を得ることができます。
ブランドの国際的な認知度向上
海外でカンファレンスを開催することは、ブランドの認知度を高める効果的な手段でもあります。参加者やメディアを通じて、自社の名前や製品、サービスが国際的に紹介されることで、新たな市場への進出や顧客基盤の拡大につながります。特に、特定の業界や分野での専門性をアピールすることができれば、その分野におけるリーダーとしての地位を確立することも可能になります。
海外でカンファレンスを開催するための準備
海外でカンファンレスを開催するために、以下のようなことをする必要があります。
- 会場選びのポイント
- 言語の壁を乗り越える方法
- ビザや入国管理について
会場選びのポイント
会場選びは、海外でのカンファレンス成功の鍵を握ります。アクセスの良さ、収容人数、設備の充実度など、基本的な要件を満たすことはもちろん、地元の文化や習慣を反映した場所選びが参加者にとっての魅力となります。また、現地の交通機関や宿泊施設との連携も重要です。参加者がスムーズに会場に到着し、快適に滞在できるようにすることで、イベント全体の満足度を高めることができます。
言語の壁を乗り越える方法
言語の壁は、海外でのイベント開催における大きな課題の一つです。この課題を解決するためには、通訳サービスの利用や、多言語対応の資料の準備が必要です。また、イベントのウェブサイトやアプリを多言語対応にすることで、事前の情報提供や当日の案内をスムーズに行うことができます。さらに、参加者同士のコミュニケーションを促進するために、言語交換の機会を設けるなどのアプローチも有効的です。
ビザや入国管理について
海外からの参加者を迎える際には、ビザの取得や入国管理の手続きが必要になる場合があります。これらの手続きは、参加者にとって大きな負担となることがあるため、イベント主催者としては、事前に必要な情報を提供し、可能な限りサポートを提供することが重要です。例えば、公式な招待状の発行や、ビザ取得のための書類作成のアシストなどが挙げられます。また、参加者がスムーズに入国できるよう、現地の大使館や領事館との連携も検討する必要があります。このように、海外でのカンファレンス開催は、多くのメリットをもたらすと同時に、様々な課題に直面します。しかし、適切な準備と対策を行うことで、これらの課題を乗り越え、成功に導くことが可能です。
成功事例と失敗談
カンファレンスを成功させるためにこれまでの事例を参考にする必要があります。
成功事例の分析
成功事例を分析することで、海外でのカンファレンス開催における重要な成功要因を明らかにします。例えば、事前の市場調査を徹底して行い、ターゲットとなる参加者のニーズや関心を正確に把握した事例、または、現地の文化や習慣を尊重し、地元のコミュニティと密接に協力してイベントを企画した事例などが挙げられます。これらの事例からは、適切な準備と地元への配慮が、参加者にとって忘れられない体験を提供し、イベントの成功につながることがわかります。
失敗から学ぶ教訓
一方で、失敗談からは、避けるべき落とし穴や、予期せぬ課題への対処法を学ぶことができます。例えば、言語の壁や文化的な違いを十分に考慮しなかったことによるコミュニケーションの失敗、不十分な現地調査による会場選びのミス、または、ビザ取得の遅れによる参加者の不参加などが挙げられます。これらの失敗談は、海外でのイベント開催において、細部にわたる注意と、柔軟な対応がいかに重要であるかを教えてくれます。
カンファレンス海外開催における法的な注意点
海外でカンファレンスを開催する際には日本よりも法的に注意する必要があります。特に大切な項目を3つ説明します。
- 各国のイベント開催法規
- 知的財産権の保護
- データ保護規則(GDPRなど)
各国のイベント開催法規
カンファレンスを海外で開催する際、開催国の法律を事前に確認し、遵守することが重要です。イベント開催に関連する法規は国によって異なるため、十分な調査が不可欠です。例えば、日本の場合は「集会及び集団示威行為の規制に関する法律」などが適用されます。一方、米国ではイベント開催の際の規制は州ごとに異なるため、開催地の州法を確認する必要があります。また、イベントの募集方法や看板・チラシの掲示にも規制がある場合があります。違反すると、イベントの中止や罰金刑を受ける可能性もあるため、法的手続きは慎重に行いましょう。
知的財産権の保護
カンファレンスでは様々なアイデアや技術が披露・共有されることから、知的財産権を侵害しないよう細心の注意を払う必要があります。特に海外で開催する場合、開催国の知的財産権法制度を確認し、対策を講じることが大切です。例えば、発表資料への著作権表記や、AI・IoTなどの先端技術にまつわる特許問題への対処方法などを事前に検討しましょう。万が一トラブルが起きた場合の対応フローも作成し、スタッフに周知徹底させることをお勧めします。
データ保護規則(GDPRなど)
近年、個人情報の保護を目的としたデータ保護規則が世界各国で施行・強化されています。特に欧州連合(EU)が2018年に施行した一般データ保護規則(GDPR)は、EU圏外で事業を行う企業にも大きな影響を及ぼしています。カンファレンスではスピーカーや参加者の個人情報を取り扱うことから、開催国のデータ保護規則を必ず把握し、遵守する必要があります。具体的には、個人情報の収集目的を明確化したうえで、本人の同意を得ること、個人データの第三者提供をしないことなどがルールとして定められています。データ漏洩に備え、情報管理体制を整備し、インシデント発生時の対応手順も決めておきましょう。
カンファレンス海外開催のためのチェックリスト
事前準備のリスト
海外でのカンファレンス開催に向けて、事前に行うべき準備は多岐にわたります。まずは開催概要を固め、目的・コンセプト・テーマ・対象者・規模を明確化しましょう。次に会場を確保します。立地条件・座席数・設備など、目的に合った会場を選ぶことが重要です。早期の予約がおすすめです。その後、スピーカーやスポンサー企業などの手配を進め、プログラム構成を詰めていきます。
プロモーション施策の立案も欠かせません。ウェブサイトやSNSでのPR、メールマガジン、プレスリリース、ダイレクトメールなど、複数の媒体を活用し、対象者に応じた効果的な手法を組み合わせましょう。 スタッフの手配や資金計画の策定、保険加入の検討、運営マニュアル作成なども行います。最後に、ビザ取得や税関手続き、出入国管理事務所への届出など法的義務の確認漏れがないか再チェックしましょう。
開催中のチェックポイント
当日は、受付・案内・会場設営などの運営体制を適切に構築する必要があります。受付時の参加登録確認や入場制限、会場アクセスや動線の案内、会期中の情報発信など、参加者の動きに合わせた運営が求められます。講演は時間厳守かつスムーズな進行を心がけ、トラブル発生時の対処方法も決めておきましょう。休憩中のケータリングサービスや各種設備の確認、ゴミ回収なども手落ちがないよう注意しましょう。また、デバイス充電スポットやWi-Fi環境の整備なども忘れずに。セッション中は資料の共有方法も検討が必要です。次年度も開催する場合、参加者の様子や質問事項を記録し改善しましょう。
閉会後のフォローアップ
カンファレンス終了後も、運営は継続して行う必要があります。まずは会場の原状回復を確実に行いましょう。次に、参加者への控えめなフォローアップが重要です。アンケートの実施により参加者の声を収集・分析し、次回の企画に活かすことができます。感謝のメールや報告書の送付なども好評です。講演者には別途、講演内容や会場運営に関するフィードバックを求めるといいでしょう。
会計処理も欠かせません。支出全般の収支決算を行い、単年度収支をしっかりと締めくくる必要があります。決算報告書を作成し、運営スタッフやスポンサー企業に送付しましょう。
最後に、知的財産権の問題が発生していないか確認します。著作権やアイデア・発明の流出などがなかったかチェックしてください。トラブルが見つかった場合は、迅速に対応し、再発防止策を立てましょう。
カンファレンス海外開催に関するよくある質問
資金調達の方法は?
カンファレンス運営には多額の資金が必要となります。主な調達方法として「参加費徴収」「スポンサー企業募集」「補助金活用」などがあげられます。参加費徴収では、適正な料金設定が求められます。高額すぎると参加者が集まらず、低額すぎるとコスト回収が難しくなります。同業他社の事例を参考に、適切な水準を見極める必要があります。
また、スポンサー企業の募集も大きな収入源になり得ます。ただし、過度な広告展開は参加者の反発を招くリスクがあり、バランスが重要です。スポンサーメリットを具体化し、協賛へのインセンティブを高めることが肝心です。
その他、開催地の自治体や業界団体などから助成金や補助金を受けられる制度があれば、積極的に活用するのも有効です。申請手続きには時間を要するため、早期の情報収集と準備が不可欠です。資金計画は予算額の段階的な精査と、確保方法の複線化が賢明です。
日本で開催する場合は自治体などから補助が受けられる場合があります。
参加者へのベストなコミュニケーション方法は?
参加者とのコミュニケーションは大切な運営ポイントです。カンファレンス公式ウェブサイトを中心に、分かりやすい情報発信に努めましょう。開催コンセプトや目的、プログラムなどの基本情報に加え、開催地の地理・気候・文化事情なども提供すると参加者にとって有益です。
事前の告知とフォローアップを徹底するため、メールマガジンの発行もおすすめです。登録者に定期的に最新情報をお知らせでき、リマインドにもなります。SNSとの連携で拡散力もアップ。Twitterなどを活用し、ハッシュタグ付きで更新ニュースを流すと効果的でしょう。
当日は、スタッフによる分かりやすい案内表示と実際の誘導を心がけてください。困っている参加者がいれば、積極的に声をかけるなどの対応が好感されます。また、アプリを導入し、詳細プログラム案内や質疑応答機能などをアプリで実現できれば便利です。
終了後は、参加者アンケートを収集し、次回に活かすよう努力を怠らないことが重要です。感想やクレーム、改善要望に真摯に耳を傾け、フォローアップのメールを送付しましょう。一過性のイベントに終わらせず、継続的な関係構築を目指すことが成功への鍵となります。
保険は必要か?
海外でカンファレンスを開催する場合、何らかの保険に加入しておくことをお勧めします。主な補償対象として、事故やトラブルなどによる主催者側の賠償責任と、参加者の傷害が想定されます。
具体的には、イベント主催者賠償責任保険がおすすめです。これは主催者側の過失により、参加者や第三者に損害を与えた場合の補償を受けられる保険です。会場設備の損壊や、参加者のケガなどに備えられます。
海外渡航者に対する補償として、海外旅行保険の加入も検討しましょう。開催国の医療費の補償だけでなく、病気やケガ、旅行変更、賠償責任などをカバーできます。
さらに、講演者や出展企業などに対するリスクにも注意が必要です。具体的には、講演会場で発生した事故への備えや、展示物の損傷への補償などがあげられます。
これらの保険加入を検討する際は、保険会社に正確な情報開示を行い、的確な保障内容を確認するようにしましょう。保険料を節約したくてもムリのない範囲で、手薄な保険は避けるべきです。緊急事態に備え、充分な補償の確保が重要です。
緊急時の対応計画は?
カンファレンス開催中に緊急事態が発生することも想定されます。災害の発生、事件・事故の発生、感染症の蔓延などに備え、対応計画を事前に策定しておく必要があります。
例えば、地震や火災などの自然災害が発生した際は、参加者の安全確保が最優先されます。落ち着いて避難誘導を行い、会場への放火や爆破などの人為的な災害が危惧される場合は、速やかに警察に連絡しましょう。
会場でのケガ、急病人の発生にも対処できるよう、応急手当を行える体制を用意しましょう。医務室の設置、AED(自動体外式除細動器)の設置、近隣の病院との連携などが有効です。スタッフには救命講習などの医療知識の習得も求められます。
まとめ
海外でのカンファレンス開催は、多大な努力と準備を要しますが、その成果は計り知れないものです。グローバルなネットワークの構築、国際的な知見の共有、ブランド認知度の向上など、そのメリットは多岐にわたります。
その他
カンファレンスを開催する際にチケットを販売する必要があります。日本のプレイガイドでは海外に向けてチケットを販売することは難しい状況です。しかし、 「TicketMe海外販売」は、既存のプレイガイドとは違い海外の方もチケットを購入できるようなサービスを展開しています。
関連記事:日本国内のチケットの販売手数料比較
TicketMe について
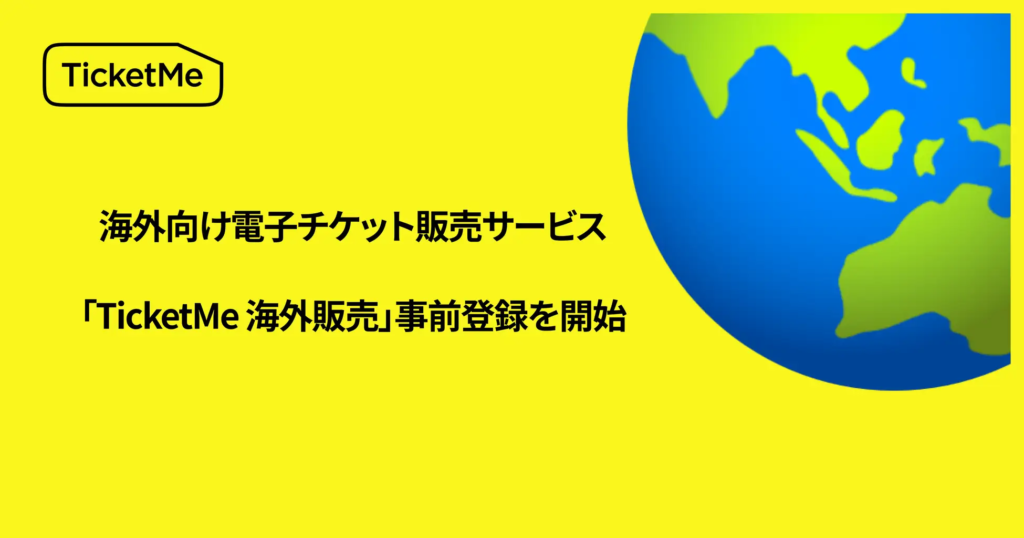
TIcketMeは日本初のNFTチケットプラットフォームです。暗号資産を使わずに、日本円などを使用して取引ができます。TicetMeの特徴は、不正転売を防ぐことができる点と2時流通が起きた際に2次流通の1部が主催者に支払われる点です。これまでは転売されても主催者側にはメリットはありませんでしたが、TicketMeではメリットは少なからずあります。また、2次流通の価格上限を主催者側が設定できるため、チケットの代金の高騰を防ぐことも可能です。これまで、ホリプロや東宝、梅芸、パルコなどの大手企業も導入しています。
関連記事:NFTチケットとは?メリットやデメリット、販売方法などを解説!
TicketMe 海外販売では、チケットを海外の人に向けての販売システムやその他サポートを提供します。以下のものを提供します。
- 訪日外国人への効果的なマーケティング
- チケット販売のオンラインシステム/決済手段の提供
- 開催日における外国人向けオペレーションのサポート
(1)訪日外国人への効果的なマーケティング
イベント事業者には、海外への効果的なマーケティングを行う人材やノウハウを保有していないなど様々な問題を抱えていると思います。しかし、チケミーでは海外の提携メディアへの、完全成果報酬型広告の出稿等のプロモーション、世界各国の開発パートナーとの連携し、国や地域ににローカライズした上で共通在庫化された販売サイトの提供により、効果的に認知、告知をすることができます。また、完全報酬型であるため、インバウンドを取り込むためのマーケティング費用を最大限まで減らすことができます。
(2)チケット販売のオンラインシステム/決済手段の提供
国々によって人気な決済方法が違っており、イベント主催者が全ての決済方法を導入することは難しいです。TicketMe 海外販売では、訪日外国人でも利用しやすいオンラインチケット販売システムを提供することは勿論のこと、クレジットカードやPayPal、Alipayなど、訪日外国人から人気の高い決済手段も幅広く対応していく方針です。購入から入場まで一貫してオンラインで完結できるシステムのため、訪日外国人やイベント主催者側も両方が利便性の高いシステムを活用することができます。
(3)開催日における外国人向けオペレーションのサポート
イベント主催者にとって外国人の対応をすることが難しい場合があります。しかし、チケミーでは、外国人への対応ができる人材の派遣を行います。これにより、イベント主催者は、外国人参加者への対応にかかる負担を軽減し、安心してイベント運営を行うことができます。
導入の流れ
「TicketMe 海外販売」の導入は、以下の流れで進めることができます。
①事前登録
以下の事前登録用のページからお問い合わせしてください。
https://ticketme.co.jp/contact/oversea
②ご相談・カスタマイズ
事業主様、配券担当者様との初回ミーティングを通じて、お客様のニーズやイベントの特性を把握し、最適なサービスを提案いたします。具体的には以下の中からお客様に必要なものを組み合わせます。
・基本機能(電子チケット販売、外国人向け決済手段の提供、二次流通コントロール機能)
・イベント詳細内容の英語対応
・海外のチケミー提携メディアへの、完全成果報酬型広告の出稿等のプロモーション
・共通在庫化した上で、国や地域にローカライズされた販売サイトでの販売
・開催日における外国人向けオペレーションのサポート
③ご導入の決定
ご相談の上で提案にご満足いただけましたら、基本的な契約手続きに移ります。契約書の取り交わしと同時に、専属の担当者がお客様にアサインされ、円滑なサービス提供のための調整が始まります。
④マーケティング戦略の立案
チケミー社の海外販売の専門家チームが、お客様のイベントに適したマーケティング戦略を立案します。提携メディアへのプロモーションや、国や地域にローカライズされた販売サイトでの販売など、訪日外国人にアプローチするための戦略が具体的に定められます。
⑤外国人向けオペレーションの計画
開催当日の外国人向けオペレーションをサポートするため、必要な人材やサービスを計画します。これには、外国人向けの入場受付や会場案内、トラブル対応などが含まれ、円滑なイベント運営のための体制が整います。
⑥トライアル運用
システムの運用や外国人向けサポートの一部をトライアル運用し、問題がないか確認します。トライアル運用の段階では、必要に応じて微調整を行い、サービスが円滑に提供できるよう最終調整を行います。
⑦本格運用開始
すべての段階が順調に進んだ場合、本格的な運用を開始します。「TicketMe 海外販売」のサービスを通じて、訪日外国人を効果的に引き込みながら売り上げを最大化し、主催者様は安心してイベントに集中できるようになります。
ご興味のある場合は、こちらからご資料を請求していただけると幸いです。
インバウンドイベントの記事
参考
株式会社チケミー | イベント業界で急拡大するインバウンド需要取り込みのための、海外向け電子チケット販売サービス「TicketMe 海外販売」の事前登録を開始。

