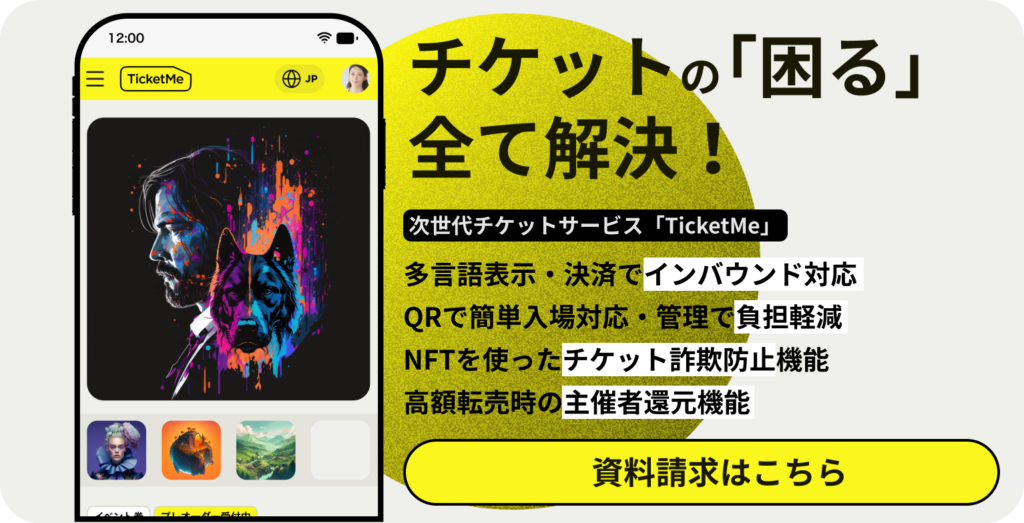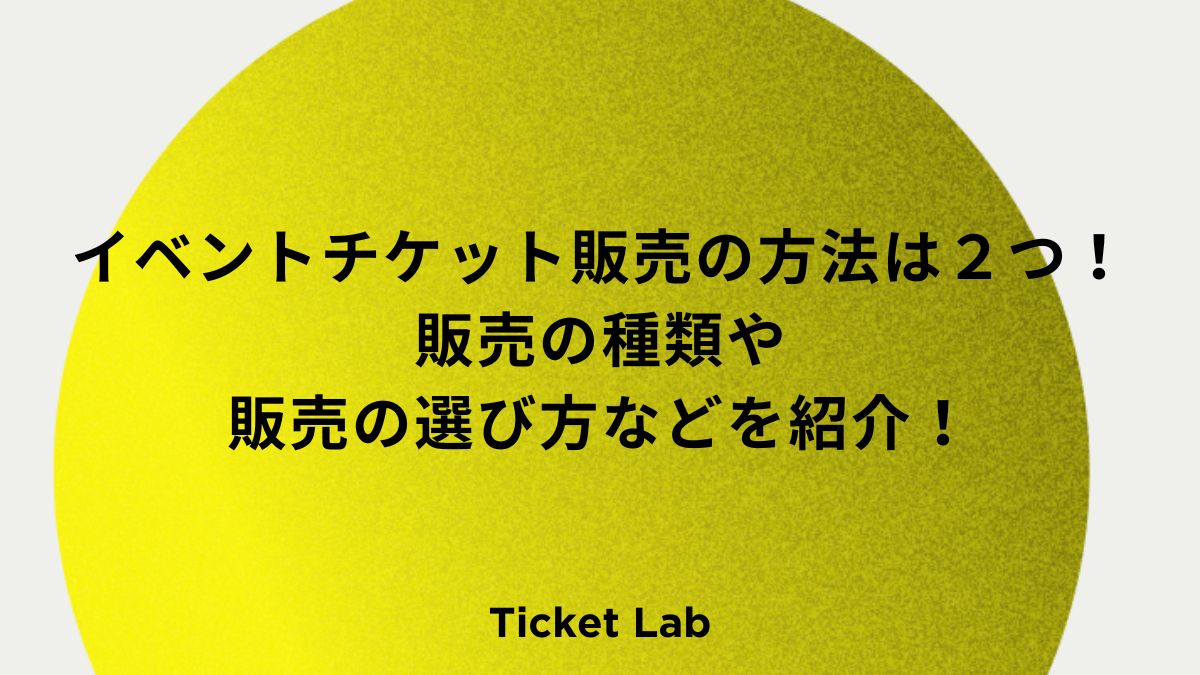「イベントを開催するけれど、チケット販売をどうすればいいのか分からない…」「効率的に販売・管理する方法はないだろうか」とお悩みではありませんか?イベント成功の鍵を握るのは、実はチケット販売方法の選択にあります。
本記事では、イベントチケット販売の基本から最新のデジタル販売プラットフォームまで、イベントを成功に導くための具体的な方法を解説します。
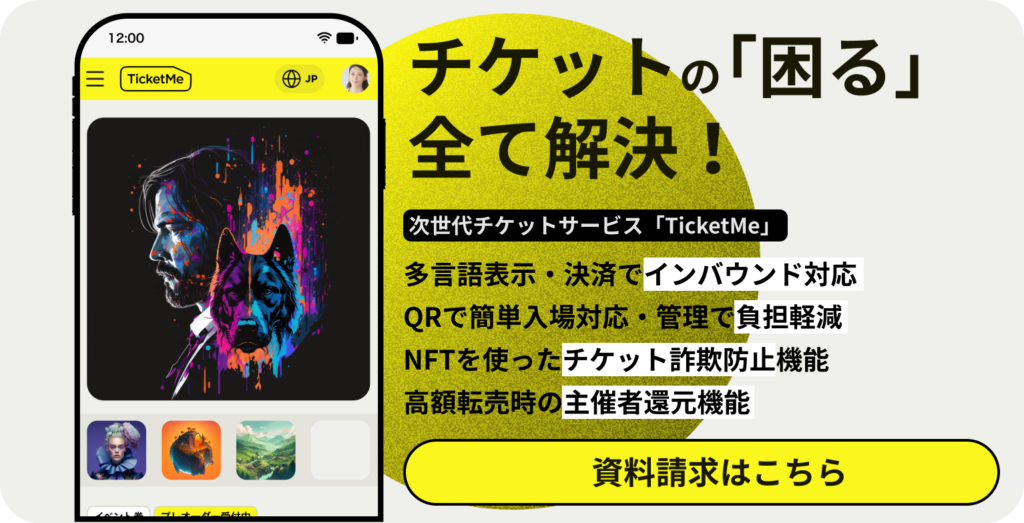
イベントチケット販売の方法は主に2つ
イベントを成功させるカギは、効果的なチケット販売戦略にあります。主催者として最初に考えるべきは「どうやってチケットを販売するか」という点です。チケット販売方法は大きく分けて「オンライン」と「オフライン」の2つがあり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
イベントの規模や対象者、予算によって最適な方法は異なるため、両方の特徴を理解した上で、自分のイベントに合った販売方法を選びましょう。
オンライン販売
オンライン販売は、インターネットを通じてチケットを販売する方法です。専用のチケット販売プラットフォームやECサイト、SNSなどを活用し、24時間いつでもどこからでも購入できる利便性が最大の魅力です。
特に近年は、スマートフォンの普及により、移動中や寝る前など、ユーザーの「ちょっとした時間」にチケットを購入するケースが増えています。オンライン販売では、決済からチケット発行までの一連の流れが自動化されるため、人的リソースを大幅に削減できます。
オンライン販売の具体的な方法としては、Peatix、チケットぴあ、イープラスなどの専門プラットフォームを利用する方法が一般的です。これらのサービスでは、イベント情報の掲載からチケット販売、入場管理までをワンストップで提供しています。
さらに、自社のWebサイトに決済機能を組み込んで販売する方法や、InstagramやFacebookなどのSNSと連携させた販売方法も効果的です。特にターゲット層がSNSを活用している若年層の場合、SNS経由の販売は高い成約率を期待できます。
オンライン販売のメリットは、地理的制約がなく全国、さらには海外からも参加者を集められることです。また、販売状況をリアルタイムで確認できるため、マーケティング戦略の調整が容易になります。さらに、購入者の属性データを収集・分析することで、次回のイベント企画に活かせるという大きなメリットもあります。
一方、デメリットとしては、システム利用料や決済手数料などのコストがかかることや、高齢者など一部のデジタルリテラシーが低い層へのアプローチが難しい点が挙げられます。また、システムトラブルが発生した際の対応策も事前に検討しておく必要があります。
オフライン販売
オフライン販売は、実店舗や会場での直接販売、電話予約、FAX申込などインターネットを介さない従来型の販売方法です。特に地域密着型のイベントや、高齢者向けのイベントでは、オフライン販売が今でも重要な役割を果たしています。
具体的な方法としては、イベント会場近くの店舗での前売りチケット販売、提携店舗でのチケット取り扱い、当日券販売所の設置などがあります。また、電話予約を受け付け、指定の口座に入金確認後にチケットを郵送するという方法も一般的です。
オフライン販売の最大のメリットは、対面での説明や勧誘ができる点です。イベントの魅力を直接伝えることで、迷っている方の背中を押すことができます。また、高齢者や現金決済を好む層にとっては、馴染みのある安心できる購入方法となります。
一方、デメリットとしては、人的コストや時間的コストがかかること、販売可能な時間や場所が限られること、販売状況の把握に時間がかかることなどが挙げられます。また、天候や災害などの影響を受けやすく、計画通りに販売が進まないリスクもあります。
チケット管理の手間も無視できません。手作業での名簿管理や入場確認は、大規模なイベントになるほど煩雑になります。特に当日の混雑を避けるためには、効率的な受付システムの構築が必要です。
イベントチケットの種類も2種類
イベントのチケットは、形態によって「紙チケット」と「電子チケット」の2種類に大別されます。それぞれに独自の特徴やメリットがあり、イベントの性質や参加者層によって最適な選択は変わってきます。主催者として両方の特性を理解し、イベントの目的や参加者の利便性を考慮した上で選択することが重要です。
近年はデジタル化の流れを受けて電子チケットの普及が進んでいますが、紙チケットならではの価値も依然として高く評価されています。
紙チケット
紙チケットは、物理的な紙媒体に印刷されたチケットのことです。従来型のチケットとして長い歴史があり、コンサート、演劇、スポーツイベントなど様々な場面で使用されています。
紙チケットの最大の特徴は、「形に残る」という点です。特に記念性の高いイベントでは、チケット自体がメモリアルアイテムとなります。ファンにとって、お気に入りアーティストのライブチケットは大切なコレクションの一部となることも少なくありません。実際に手に取れる実物があることで、イベントへの期待感や高揚感を高める効果もあります。
デザイン面では、紙チケットは自由度が高く、イベントの世界観やブランドイメージを反映させたクリエイティブな表現が可能です。特殊紙や箔押し、エンボス加工などの特殊印刷技術を用いることで、高級感のある仕上がりを実現できます。
また、紙チケットは偽造防止対策として、ホログラムシールや特殊インク、QRコード、バーコードなどを組み合わせることで、セキュリティ性を高めることができます。特に高額チケットのイベントでは、こうした対策は不可欠です。
一方で、紙チケットには発行コストや配送コストがかかるというデメリットがあります。また、紛失や盗難のリスクもあり、再発行に関するルールや対応策を事前に決めておく必要があります。入場管理の面では、バーコード読み取りなどのシステムを導入しない限り、目視確認となるため、大規模イベントでは入場に時間がかかる場合があります。
電子チケット
電子チケットは、デジタルデータとして発行・管理されるチケットのことで、スマートフォンやタブレットなどの端末で表示・利用します。QRコードやバーコードを用いたものが一般的で、専用アプリやメール、ウェブサイト上で配布されます。
電子チケットの最大の特徴は、その利便性の高さです。チケットの購入から入場までの一連のプロセスがデジタル上で完結するため、発券や郵送の手間が不要となります。購入後すぐにチケットを受け取れるため、直前の駆け込み需要にも対応可能です。
また、スマートフォン一つでチケットを管理できるため、紛失のリスクが大幅に軽減されます。複数人分のチケットも一括管理が容易で、友人や家族との共有もスムーズに行えます。
運営側にとっても、電子チケットには多くのメリットがあります。発行コストの削減はもちろん、データ管理が容易になるため、販売状況のリアルタイム把握や入場管理の効率化が実現します。特に入場時のQRコードスキャンは、従来の目視確認に比べて格段に速く、入場口での混雑緩和につながります。
さらに、不正転売対策としても電子チケットは有効です。顔認証と連動させたり、入場直前にのみQRコードを表示させるなどの機能により、チケットの不正利用を防止できます。実際に、大手興行会社や音楽フェスティバルなどでは、こうした機能を備えた電子チケットの導入が進んでいます。
マーケティング面では、購入者の属性データや行動パターンの収集・分析が容易になるため、よりターゲットを絞った販促活動が可能になります。
一方で、デメリットとしては、高齢者などデジタル機器に不慣れな層へのサポートが必要になる点や、通信環境やバッテリー切れなどのトラブルに対する対策が求められる点が挙げられます。また、記念品としての価値を求めるファンにとっては、物理的な形がない点が物足りなく感じられることもあります。
関連:電子チケットとは?導入するメリット、デメリットなど解説!
イベントチケットを販売の選び方は?
イベントチケット販売サービスを選ぶ際には、単に手数料の安さだけで判断するのではなく、複数の視点から総合的に評価することが大切です。
イベントの規模や性質、ターゲット層に合わせて最適なサービスを選ぶことで、集客力の向上やスムーズな運営につながります。以下では、チケット販売サービスを選ぶ際のポイントを詳しく解説していきます。
座席情報を詳細に確認する
チケット販売サービスを選ぶ際、座席情報の表示方法や管理機能は非常に重要なポイントです。特に座席指定のあるイベントでは、参加者が自分の希望する座席を視覚的にわかりやすく選べるかどうかが購入体験を大きく左右します。
座席表示のビジュアル性に優れたプラットフォームでは、会場の座席マップを詳細に再現し、各座席からのステージの見え方や距離感がイメージしやすくなっています。これにより、参加者は自分の希望に合った位置を選びやすくなり、購入後の「思っていた席と違った」といった不満を防ぐことができます。
また、座席の段階的な販売機能も確認しておくべきです。VIP席や先行販売席、一般席など、異なる種類の座席を時期をずらして販売する場合、その設定がシステム上で柔軟にできるかどうかをチェックしましょう。
さらに、座席の空き状況がリアルタイムで反映されるかどうかも重要です。特に人気イベントでは、購入者が座席を選んでいる最中に他の人に取られてしまうというストレスを防ぐため、セッションタイムアウトや仮押さえ機能があるサービスが望ましいです。
手数料を比較する
チケット販売サービスを選ぶ際、手数料体系は収益に直接影響する重要な要素です。各サービスによって手数料の計算方法や料率は大きく異なるため、単純な数字だけでなく、総合的なコストを比較することが重要です。
一般的なチケット販売サービスの手数料は、定額制と定率制の2種類があります。定額制は1枚あたりの固定手数料が発生するタイプで、高額チケットほど割合としては有利になります。一方、定率制はチケット価格に対する一定割合の手数料がかかるタイプで、低額チケットに適しています。
また、手数料の負担者についても確認が必要です。主催者負担型と購入者負担型があり、どちらを選ぶかによって価格設定や収益計画が変わってきます。購入者負担型を選ぶ場合は、手数料込みの金額が心理的な購入障壁にならないかも考慮しましょう。
さらに、基本手数料以外の隠れたコストにも注意が必要です。初期設定費、月額固定費、振込手数料、キャンセル時の手数料、機材レンタル費などが発生するサービスもあります。
返金・交換ポリシーを確認する
イベント運営において、返金や交換に関するポリシーは非常に重要な要素です。チケット販売サービスを選ぶ際は、柔軟な対応ができるかどうかをしっかりと確認しておくことが必要です。
まず、キャンセル時の返金条件と手続き方法を確認しましょう。返金可能な期限や、返金時の手数料控除の有無、返金方法(元の決済方法への返金か、ポイント返還か)などが明確に定められているかをチェックします。特に、イベント中止時や延期時の対応方針が明確であることは、トラブル防止の観点から非常に重要です。
次に、チケットの譲渡や転売の可否についても確認が必要です。参加できなくなった人が友人や家族に譲れるシステムがあると、キャンセルを減らすことができます。一方で、不正転売防止の観点から、譲渡に一定の制限を設けているサービスもあります。イベントの性質に合わせて、適切な譲渡ポリシーを持つサービスを選びましょう。
日程や座席の変更機能についても重要です。購入者が自分で変更操作ができるのか、主催者を通じて変更する必要があるのか、また変更時に手数料が発生するかなどを事前に確認しておくと、イベント当日の混乱を防ぐことができます。
本人確認や年齢制限を確認する
イベントの性質によっては、本人確認や年齢制限が必要になる場合があります。
本人確認機能としては、購入時の身分証明書情報登録、QRコードと身分証の照合システム、顔認証技術の活用などがあります。特に人気イベントでのチケット転売防止や、特定参加者の入場制限を行いたい場合には、確実な本人確認ができるシステムが不可欠です。
年齢確認については、購入時に生年月日の入力を必須とする機能や、未成年者の購入を制限する機能が重要です。また、保護者同伴の場合の特別ルール設定ができるかどうかも、ファミリー向けイベントでは確認しておくべきポイントです。
サポート体制について確認する
チケット販売サービスを選ぶ際、運営者向けと購入者向けの両方のサポート体制を確認することが非常に重要です。特にイベント当日やチケット販売開始直後など、重要なタイミングでのトラブル対応力は、イベントの成否を左右する要素となります。
まず、運営者向けのサポート体制としては、専任担当者の有無、問い合わせ可能な時間帯、対応言語、緊急時の連絡手段などを確認しましょう。特に初めてチケット販売システムを利用する場合は、設定のサポートや操作方法の丁寧な説明が受けられるかどうかが重要なポイントになります。
次に、購入者向けのサポート体制も重要です。チケット購入に関する問い合わせや、決済トラブル、入場方法の確認など、参加者からの質問に適切に対応できる体制があるかどうかをチェックしましょう。特にチャットサポートやSNS対応など、即時性の高いコミュニケーションチャネルが用意されているかどうかは、参加者満足度に直結します。
多言語対応の有無も、インバウンド観光客や国際的なイベントを検討している場合は重要な選定基準です。英語だけでなく、主要なターゲット国の言語でのサポートが受けられるかどうかを確認しておくと安心です。
さらに、トラブル発生時の代替手段や緊急対応プランが用意されているかどうかも重要なポイントです。例えば、システムダウン時の紙チケット対応や、QRコード読み取り不良時の手動確認方法など、予期せぬ事態に対するバックアッププランがあるサービスを選ぶことで、イベント当日の混乱を最小限に抑えることができます。
チケットを販売するならチケミーがおすすめ!
イベント運営において、効率的かつセキュアなチケット販売は成功の鍵を握ります。そこで今、多くの主催者から注目を集めているのが「チケミー」です。
チケミーは単なるチケット販売ツールではなく、イベント主催者の収益最大化を支援する総合プラットフォームです。今回は、そんなチケミーの特徴やメリットについて詳しく解説していきます。チケット販売に悩みを抱えているイベント主催者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
チケミーは、ブロックチェーン技術を活用したNFTチケット販売プラットフォームとして、他にはない独自の機能を多数備えています。最大の特徴は、NFT技術を利用することで不正転売を防止しながらも、健全な二次流通を可能にした点です。
まず、チケミーの操作性はとても直感的で、NFTや暗号資産の知識がなくても簡単に利用できます。従来の電子チケット販売プラットフォームに近い感覚で使えるため、技術的な知識がなくても安心して導入できます。チケット購入者側も、特別なウォレットや暗号資産を用意する必要はなく、クレジットカードで日本円での決済が可能です。
また、チケミーの大きな特徴として、二次流通(リセール)機能があります。従来のチケット販売では、チケットが転売されると主催者側には一切利益が還元されませんでしたが、チケミーでは二次流通が行われるたびに、その利益の一部が主催者に還元される仕組みを採用しています。主催者は二次流通の価格設定も可能なので、不当な高額転売を防ぐことができます。
さらに、チケミーではQRコードを活用した入場管理機能も充実しています。専用アプリでチケットのQRコードをスキャンするだけで、迅速かつ正確に入場を管理できるため、長蛇の列や混乱を避けることができます。入場データはリアルタイムで確認でき、イベント運営の効率化に役立ちます。
最近では抽選販売機能も追加され、高需要のチケットを適切に管理し、ファンに公平感のある購入体験を提供することも可能になりました。このように、チケミーは常に機能を強化し、主催者の売上最大化と運営効率化をサポートしています。
最後に、ファンエンゲージメントの向上も重要なメリットです。NFTチケットはデジタルコレクションとしての価値も持ち、ファンはイベント後もチケットを思い出として保管できます。これによりファンとの長期的な関係構築につながり、ファンコミュニティの醸成にも役立ちます。
まとめ
イベントチケット販売方法は、オンラインとオフラインの2つに大別され、それぞれ紙チケットと電子チケットという選択肢があります。効果的なチケット販売プラットフォームを選ぶ際は、座席情報の表示方法、手数料体系、返金・交換ポリシー、本人確認機能、サポート体制などを総合的に判断することが重要です。
イベントチケットを販売するならチケミーがおすすめです。不正転売に関して課題を持っている事業者様や外国人も購入しやすいサービスを使用したい事業者は特におすすめです。
ご興味のある事業者様はぜひ資料請求してみてください。